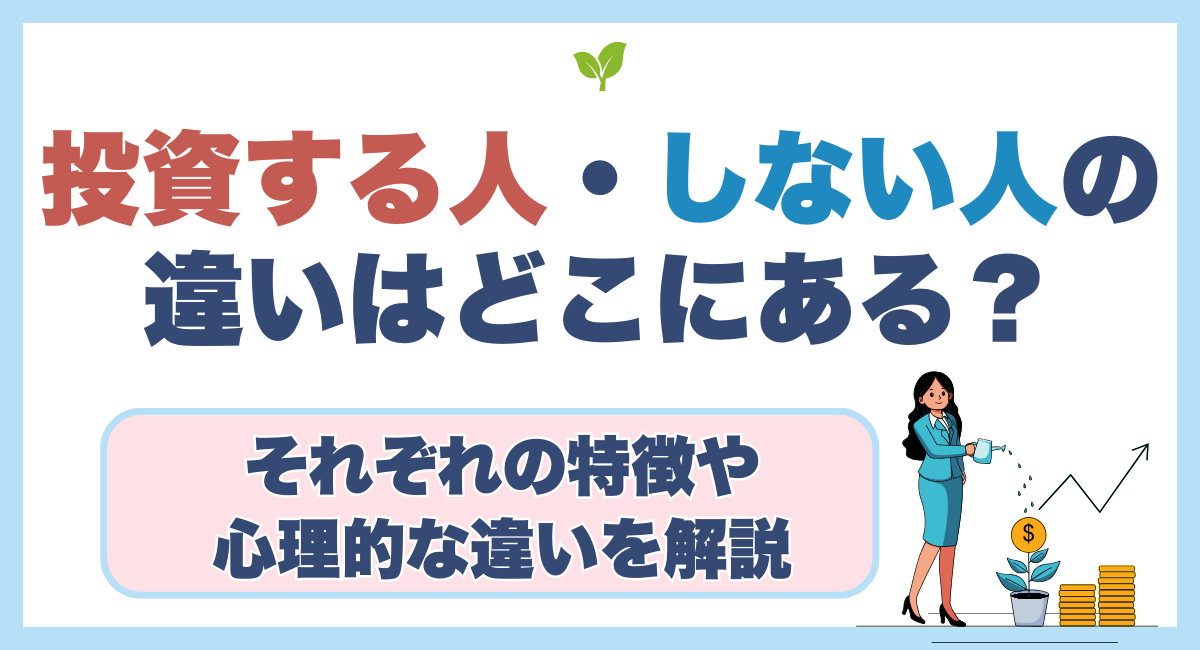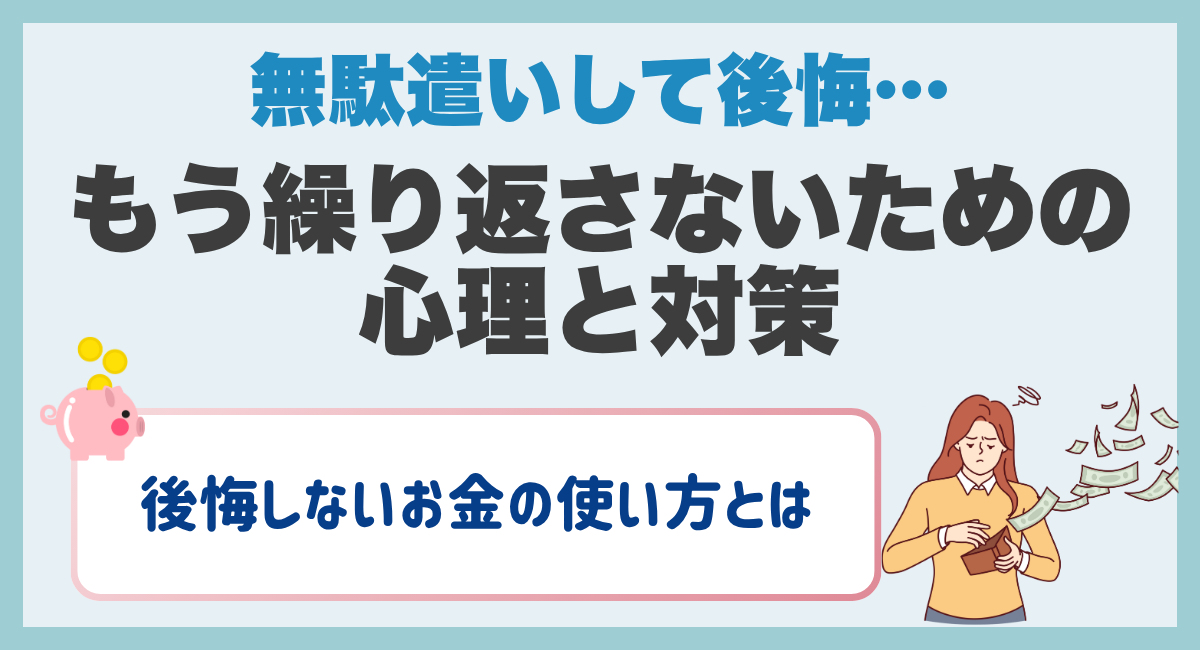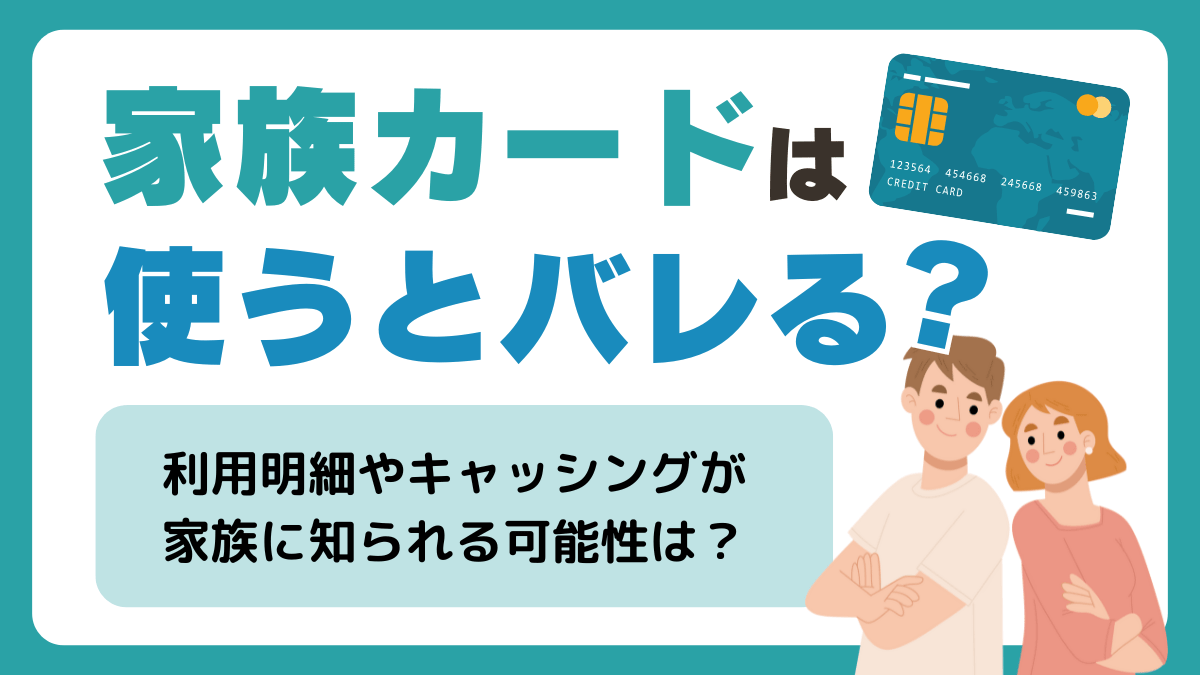同じ収入や環境であっても、「投資をする人」と「投資をしない人」では、将来の資産形成やお金に対する考え方に大きな差が生まれます。投資をする人は長期的な複利の効果を意識し、資産を増やす仕組みを整えようとします。
一方、投資をしない人はリスクを避け、現金や預金を中心に資産を守る傾向があります。本記事では両者の特徴や心理的な違いを整理し、投資を始める際の第一歩を解説します。
投資する人の特徴
将来の資産形成を意識している
投資をする人は、老後資金や教育費といったライフイベントを見据え、長期的に資産を増やそうとする傾向があります。金融庁も資産形成の基本として「長期・積立・分散」を推奨しており、少額からでも積立を始めることで将来の備えができると解説しています。
投資をする人は短期的な利益を狙うのではなく、時間を味方につけて安定した資産形成を目指しているのです。
リスクを理解し、コントロールしている
投資には価格変動や元本割れのリスクが伴いますが、投資をする人はリスクを避けるのではなく「コントロールする」姿勢を持っています。具体的には複数の銘柄や資産クラスに分散する、長期投資で一時的な下落をならすといった手法を取ります。
こうした考え方は、日本銀行が示す「家計の資金循環統計」にも表れており、株式や投資信託を組み込む人は預金だけの人より実質的なリターンを得やすい傾向にあります。
出典:日本銀行「資金循環」
情報収集と学習を欠かさない
投資をする人は、金融ニュースや公的な制度情報に日常的に触れ、判断材料を増やす習慣を持っています。金融広報中央委員会の「金融リテラシー調査」でも、投資行動を取る人ほど金融知識や行動習慣が高いことが報告されています。
情報を正しく理解し、自分に合った投資方法を選べることが、投資を継続できる人の特徴といえるでしょう。
投資しない人の特徴
元本割れの不安が強い
投資をしない人の大きな理由の一つは「元本が減るのが怖い」という心理です。預金は元本保証があるため安心感がありますが、株式や投資信託は価格が上下し、損失の可能性があります。
日本銀行の「資金循環統計」によれば、日本の家計金融資産の半分以上が依然として現金・預金で占められており、このリスク回避的な姿勢が数字にも表れています。安全志向は悪いことではありませんが、結果的にインフレで実質的な価値が目減りするリスクを抱えることになります。
出典:日本銀行「資金循環」
余剰資金や計画が不十分
投資をしない人は、生活費や緊急資金と投資資金の線引きができていない場合が多いです。家計のやりくりが不十分だと「投資する余裕がない」と考えてしまい、第一歩を踏み出せません。
金融庁の調査でも、家計の資産形成が進まない理由の一つとして「余裕資金がない」「生活費が優先される」といった回答が多く挙げられています。計画的に生活防衛資金を確保すれば、少額からでも投資を始められる可能性があります。
情報不足で踏み出せない
投資に関する基礎知識が不足していることも、投資をしない理由の一つです。特にNISAやiDeCoといった制度の存在を知らない、もしくは理解できていない人は多いとされます。
金融広報中央委員会の金融リテラシー調査でも、日本は諸外国と比べて投資や制度の知識が十分に浸透していないと指摘されています。情報不足が「不安」の根拠を補強し、結果的に行動を起こさない要因となっているのです。
投資する人としない人の心理的な違い
リスクの捉え方
投資をする人としない人では、リスクに対する捉え方が大きく異なります。投資する人はリスクを「危険」ではなく「不確実性」として理解し、分散投資や長期投資でコントロールできるものと考えます。
一方、投資しない人は「リスク=損失」と直結させやすく、結果的に現金や預金に資産を集中させる傾向があります。金融庁の資料でも「リスクを避けるのではなく管理する」という視点の重要性が繰り返し強調されています。
将来に対する姿勢
投資をする人は「将来の生活を守るために今から準備する」という前向きな姿勢を持っています。資産形成を通じて老後や教育資金を備えることが、安心感につながると理解しているのです。
一方で投資をしない人は「今を守る」ことに重点を置き、将来の課題を先送りにしがちです。金融広報中央委員会の調査でも、日本人は諸外国と比べて「長期的視点の資産形成」が弱い傾向が示されています。
情報の取り方と意思決定
投資をする人は、制度や統計といった一次情報を自分で調べ、判断材料を集める習慣があります。その結果、正しい情報に基づいた行動ができる可能性が高まります。反対に投資をしない人は、SNSや周囲の意見といった断片的な情報に左右されやすく、不安や誤解を強めてしまう傾向があります。
金融庁や日本銀行の公表資料といった信頼性の高い情報源に触れるかどうかが、心理面で大きな違いを生んでいるのです。
出典:日本銀行「資金循環」
投資をしないことのデメリット
インフレによる資産価値の目減り
投資をしない人が最も直面しやすいリスクは、インフレによる資産価値の減少です。現金や預金は元本保証があるため安心に見えますが、物価が上昇すれば同じお金で購入できる商品やサービスの量が減ります。
総務省統計局の消費者物価指数(CPI)によると、日本でも近年は物価上昇が続いており、預金金利がほぼゼロの状況では実質的に資産が減っていることになります。
老後資金不足のリスク
投資を行わないと、老後の生活資金が不足する可能性が高まります。金融庁が2019年に公表した「高齢社会における資産形成・管理」では、年金収入だけでは平均的な生活を維持できず、老後に2,000万円程度の不足が生じるケースがあると報告されています。
貯金だけではインフレに弱く、退職後に生活費や医療費を補う手段が限られるため、資産寿命を延ばす工夫が必要です。
資産形成の機会損失
投資をしないことは、資産を増やすチャンスを逃すことにもつながります。たとえば世界株式を対象としたMSCIワールド指数は、長期的には右肩上がりの成長を続けており、数十年単位で投資をしてきた人々は着実にリターンを得ています。
現金や預金のみで資産を保有していると、この成長の果実を享受できず、長期的な資産形成で大きな差が生じるのです。
投資を始めるための第一歩
少額から積立投資を試す
投資を始めるときは、少額から積立で行うのが安心です。毎月1,000円や5,000円といった小さな金額からでも積立を継続すれば、ドルコスト平均法の効果で価格変動リスクを平準化できます。
時間を味方にすることで複利の力が働き、長期的な資産形成が可能になります。投資初心者が「まず試す」一歩として、無理のない範囲から始めることが大切です。
NISAやiDeCoなどの制度を活用する
国が用意する税制優遇制度を活用することは、投資の効率を高める大きなポイントです。新NISAは2024年から非課税枠が拡大され、生涯で1,800万円まで投資益が非課税になります。さらに売却すると枠が復活する仕組みも導入され、長期投資との相性が高まりました。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)は掛金が全額所得控除の対象となり、節税と老後資金準備を両立できます。
金融リテラシーを高める習慣を持つ
投資を継続的に行うには、正しい情報に触れる習慣を身につけることが欠かせません。金融広報中央委員会の調査では、知識に加えて「行動・態度」も含めた金融リテラシーが資産形成に直結することが示されています。
経済ニュースや制度改正に関心を持ち、公的機関の発表資料など信頼性の高い情報源を活用することが、投資判断の質を高める近道です。
投資に関するよくある質問(FAQ)
投資はしない方が安全なの?
投資をしなければ元本割れのリスクは避けられますが、その一方でインフレによる資産価値の減少や資産形成の機会損失といったリスクが存在します。
安全に見えても「将来の購買力を守る」という観点では必ずしも有利とは限りません。現金と投資のバランスを取ることが現実的な選択肢です。
投資をしないと損をしているの?
必ずしも「損」とは言えませんが、投資をする人との差は長期的に大きくなります。たとえば世界株式市場(MSCIワールド指数)は長期的に成長を続けており、投資を続けた人は資産を増やしています。
投資をしない人はこの成長の果実を享受できず、結果的に資産形成で後れを取る可能性があります。
初心者はどんな投資から始めるべき?
初心者に推奨されるのは、少額からの積立投資です。金融庁も「長期・積立・分散」を資産形成の基本と位置づけ、NISAやiDeCoといった制度を活用することを推奨しています。
少額から始めることで心理的負担を抑えつつ、投資の仕組みに慣れることができます。
まとめ
「投資する人」と「投資しない人」では、将来の資産形成やお金に対する姿勢に大きな違いがあります。投資をする人は将来を意識し、リスクを理解して管理し、少額からでも長期的に資産形成を進める傾向があります。一方、投資をしない人はリスク回避を優先し、現金・預金に偏るため、インフレによる目減りや老後資金不足といった課題を抱えやすくなります。
重要なのは、極端に「投資する/しない」を二分することではなく、自分の生活防衛資金を確保したうえで、無理のない範囲で投資を取り入れることです。NISAやiDeCoといった制度を活用し、公的情報を参考にしながら少額から始めることで、安心して資産形成を続けられます。将来への備えを「知識と行動」で積み重ねることが、後悔しない選択につながるでしょう。