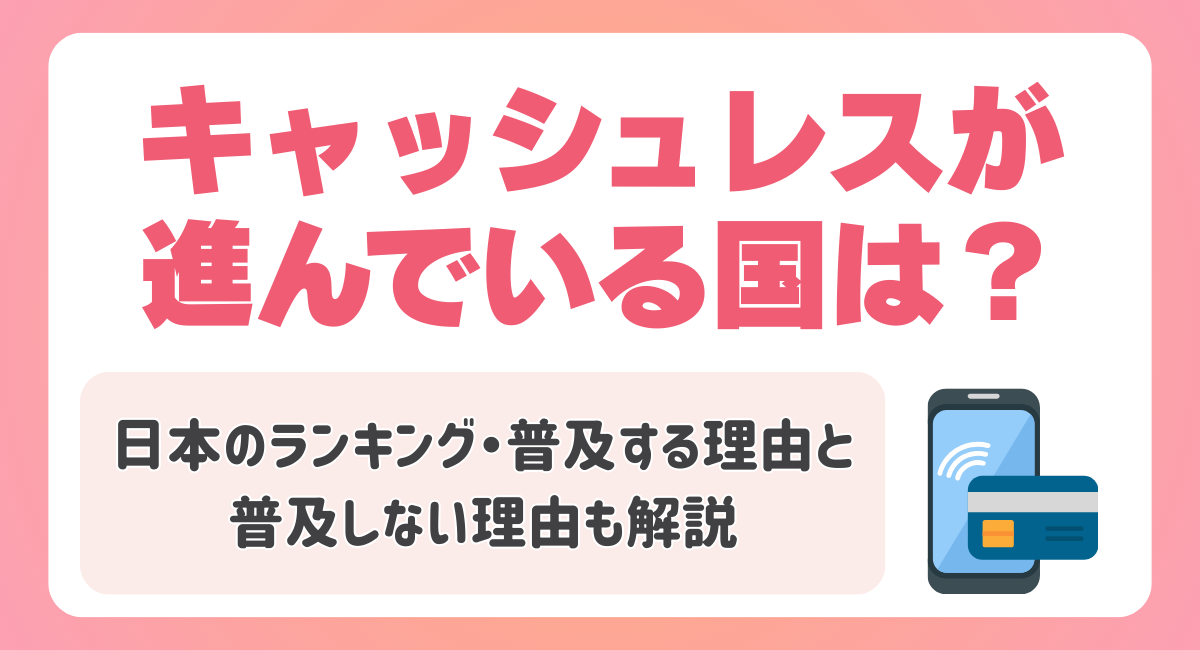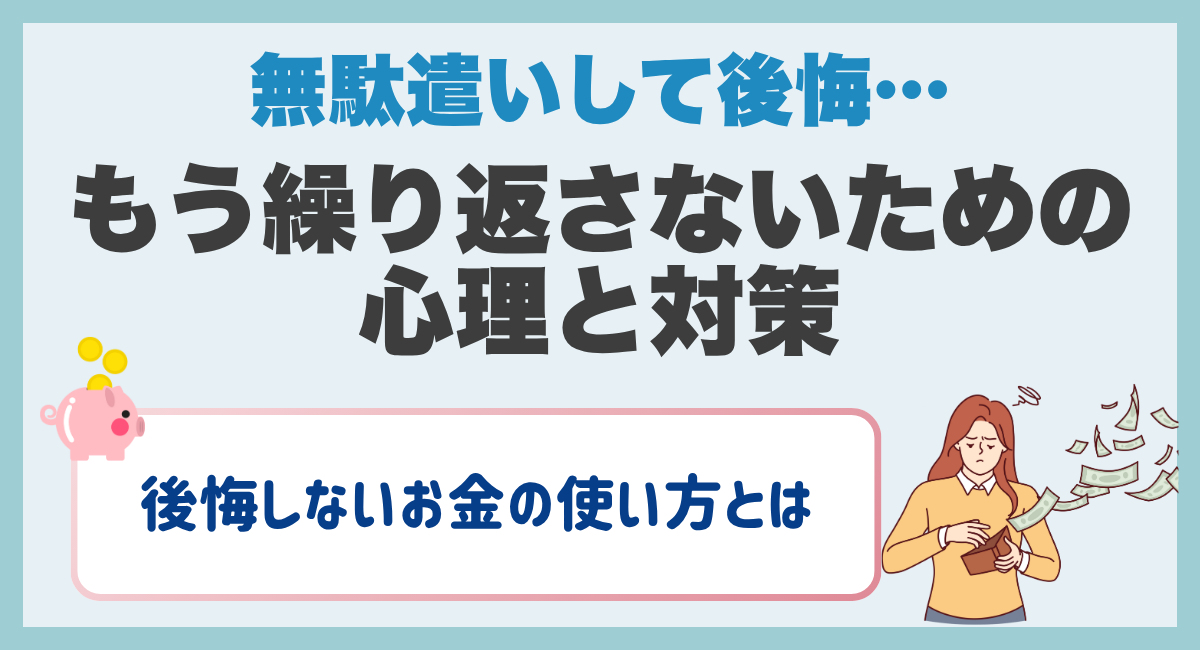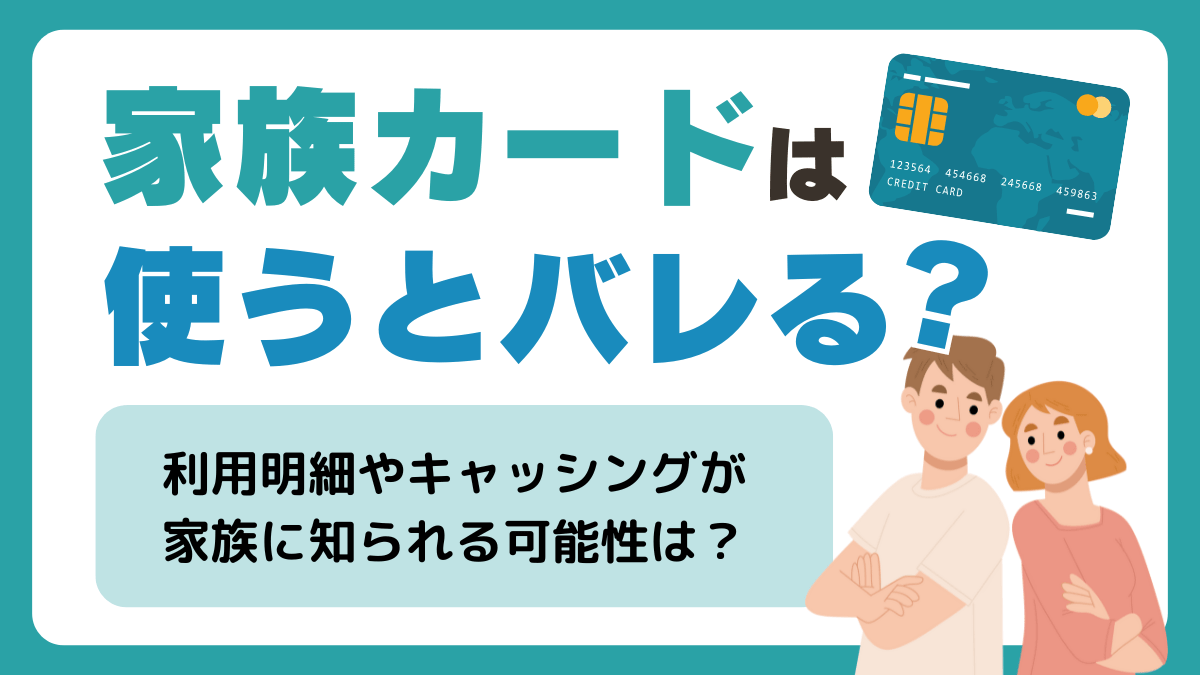キャッシュレス決済は世界的に急速に広がり、国や地域によって普及のスピードに大きな差があります。日本では近年QRコード決済や電子マネーが普及してきましたが、依然として現金の利用が根強い状況です。では、キャッシュレス化が最も進んでいる国はどこなのでしょうか?
本記事ではキャッシュレス化の基本から、キャッシュレス先進国のランキング、日本の現状と課題までを整理します。
キャッシュレス化とは?
定義(現金を使わずに支払いを行う仕組み)
キャッシュレス化とは、現金を使わずに支払いを行う仕組みを指します。具体的にはクレジットカードやデビットカード、電子マネー、QRコード決済などが代表的な手段です。国際的にも「非現金決済(cashless payment)」という用語で統一され、決済の効率化や利便性向上を目的として導入が進んでいます。経済産業省の「キャッシュレス・ビジョン」でも、キャッシュレス化を生産性向上・経済成長の要と位置づけています。
出典:キャッシュレス・ビジョン
キャッシュレス決済の種類(クレカ・QRコード・電子マネーなど)
キャッシュレス決済には多様な形態があります。クレジットカード・デビットカードは国際的に最も普及しており、電子マネー(SuicaやPASMOなど)は日本独自の発展を遂げています。さらに近年はQRコード決済(PayPay、LINE Pay、Alipayなど)が台頭し、スマートフォン一台で支払いが完結するスタイルが世界中に広がりました。これらの手段は国や地域によって主流が異なり、文化やインフラに大きく左右されます。
世界的な潮流と背景
世界的にキャッシュレス化が進む背景には、スマートフォンの普及、金融機関やテック企業によるサービス展開、そして政府の推進策があります。例えばスウェーデンでは現金をほとんど使わない社会が実現しつつあり、中国ではQRコード決済が公共料金や個人間送金まで幅広く利用されています。国際決済銀行(BIS)も「キャッシュレス決済の拡大は国際的な流れ」と分析しており、今後も加速が予想されます。
キャッシュレス化が進んでいる国ランキング
以下は公開データをもとにまとめたキャッシュレス化が進む国の例です。比率や順位は調査機関によって異なりますが、キャッシュレス先進国の傾向をつかむ上で参考になります。
| 順位 | 国名 | キャッシュレス比率・特徴 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1位 | スウェーデン | 現金利用率は取引全体の約10%以下。Swishなどモバイル送金が主流。 | Riksbank |
| 2位 | 韓国 | 政府施策でキャッシュレス比率が高水準。クレジットカード普及率も世界トップクラス。 | WEF |
| 3位 | 中国 | QRコード決済(Alipay・WeChat Pay)が社会インフラ化。都市部ではほぼ現金不要。 | MoneyTransfers |
| 4位 | イギリス | デビットカード・非接触型決済の利用が急増。現金取引は年々減少。 | Reuters |
| 5位 | カナダ | クレジットカードや非接触決済が一般化。若年層でモバイル決済が普及。 | Wikipedia |
| 参考 | 日本 | 2023年のキャッシュレス比率39.3%。2024年には42.8%に達し政府目標を前倒し達成。 | METI(経済産業省) |
スウェーデン
スウェーデンは世界で最もキャッシュレス化が進んでいる国の一つです。現金の利用はほとんど見られず、2025年のリクスバンク(中央銀行)の報告では「日常取引の現金利用率は約10%以下」とされています。スマートフォンを使ったモバイル送金アプリ「Swish」が社会インフラのように普及しており、友人間の送金から公共料金の支払いまで幅広く活用されています。店舗でも現金を受け付けないケースが珍しくなく、2030年頃には完全キャッシュレス社会になるとの見方もあります。
韓国
韓国は政府の政策によってキャッシュレス化が強力に進められてきた国です。クレジットカードの普及率は世界でもトップクラスで、国民1人当たり平均4枚以上を保有しているといわれています。また、カード決済額に応じて税制優遇が得られる仕組みもあり、現金よりもカード利用が一般的です。加えて、交通機関や小規模店舗でも電子マネーやモバイル決済が利用できる環境が整っており、国民生活に深く根付いています。そのためキャッシュレス決済の比率は常に高水準を維持しています。
中国
中国では、QRコード決済が社会のインフラとして完全に根付いています。Alipay(アリペイ)やWeChat Pay(ウィーチャットペイ)は都市部だけでなく農村部にも浸透し、屋台や個人商店でも現金を使わずにスマホで決済するのが当たり前になりました。2010年代後半から急速に普及し、現在では公共交通機関や光熱費の支払い、さらには慈善寄付に至るまで幅広く対応しています。結果として、都市生活者の大半は現金をほとんど持ち歩かずに生活しているといわれます。
イギリス
イギリスではデビットカードと非接触型決済(コンタクトレス)の普及がキャッシュレス化を牽引しています。特に新型コロナ以降、衛生面の理由から非接触決済が急増し、スーパーや小売店での主要な支払い方法となりました。イングランド銀行や業界団体の調査によれば、2023年の小売取引における現金利用は過去最低を更新しており、キャッシュレス決済が主流となっています。また、政府も金融包摂の観点からデジタル決済の推進に取り組んでいます。
出典:UK cash usage falls to record low share of transactions in 2023
カナダ
カナダはクレジットカード利用率が高く、非接触決済の普及も進んでいる国です。VisaやMastercardだけでなく、デビットカードやApple Pay・Google Payといったモバイル決済も広く利用されています。若年層ではスマートフォンによる支払いが日常化しており、特に都市部では現金を持ち歩かなくても生活できる環境が整いつつあります。さらに、金融機関や政府がセキュリティや利便性の強化に力を入れていることから、キャッシュレス比率は年々上昇しています。
キャッシュレスが進む要因
政府の政策(税制優遇・キャッシュレス推進策)
キャッシュレス化が進む大きな要因のひとつは、政府の政策による後押しです。韓国ではクレジットカード利用額に応じて税控除を受けられる制度が導入され、利用率が世界トップクラスに達しました。中国では政府がモバイル決済事業者を認可し、規制と普及を同時に進めることでAlipayやWeChat Payが社会インフラとなりました。日本でも経済産業省が「キャッシュレス・ビジョン」を策定し、2025年までに決済比率40%を目標に掲げてきました。こうした政策的な推進が、各国で普及を加速させています。
出典:キャッシュレス・ビジョン
技術・インフラの発展(スマホ普及、通信環境)
スマートフォンの普及と通信環境の整備も、キャッシュレス化の大きな要因です。特に中国ではスマホの爆発的な普及と4G通信網の整備が、QRコード決済の急速な浸透を可能にしました。スウェーデンやフィンランドでは高速通信環境とデジタルバンキングの整備により、非接触決済がスムーズに利用できる環境が整っています。また、クラウド決済やフィンテック企業の登場により、銀行以外の事業者が提供する決済手段も増え、利用者にとって選択肢が広がっています。
国民の文化・習慣(現金信頼度の違い)
文化や習慣もキャッシュレス普及のスピードに大きな影響を与えます。スウェーデンや韓国では現金よりもデジタル決済を好む国民性があり、社会全体で「現金を持たないことが普通」となっています。一方、日本では治安の良さや偽札の少なさから現金への信頼が厚く、現金志向がキャッシュレス普及の遅れにつながってきました。また、高齢者層のデジタル利用に不安がある点も課題です。国民の価値観や生活習慣が、キャッシュレスの浸透に直結していることが分かります。
日本はなぜ遅れているのか?
現金信仰の文化(治安の良さ、偽札が少ない)
日本がキャッシュレス化で遅れをとってきた背景には、現金に対する信頼感の高さがあります。日本は治安が良く、偽札もほとんど出回らないため、現金を持ち歩いてもリスクが小さいと考えられてきました。さらにATM網が全国に整備され、いつでも現金を引き出せる環境も現金志向を後押ししています。経済産業省も「現金信仰が強いことがキャッシュレス普及の壁」と指摘しており、文化的な背景が普及スピードの差を生み出しています。
出典:キャッシュレス・ビジョン
高齢者の多さとデジタルリテラシーの課題
日本は高齢化が進んでおり、デジタルサービスへの抵抗感を持つ世代が多いこともキャッシュレス化の遅れに影響しています。特にスマートフォンやQRコード決済に不慣れな高齢者層では、現金を使い続ける傾向が強く見られます。総務省の調査でも、高齢世代ほどキャッシュレス決済の利用率が低いことが明らかになっています。若年層を中心に普及が進む一方で、世代間格差が日本全体の普及率を押し下げる要因になっているといえるでしょう。
出典:通信利用動向調査
中小店舗での導入コスト問題
キャッシュレス決済には端末やシステム導入のコストがかかり、中小企業や個人商店では負担となるケースがあります。特にQRコードや電子マネーの決済手数料は店舗側の利益を圧迫するため、導入を敬遠する店舗も少なくありません。経済産業省の資料でも「中小規模事業者での導入遅れ」が普及の課題として挙げられています。キャッシュレス決済を全国的に浸透させるには、事業者への支援や手数料の見直しが不可欠といえるでしょう。
出典:キャッシュレス・ビジョン
キャッシュレス化のメリット
キャッシュレス化には、消費者、事業者(店舗)、社会全体のそれぞれに大きなメリットがあります。
消費者・事業者、社会全体のメリットを確認していきましょう。
消費者のメリット
- 支払いの迅速化と利便性向上
現金や小銭を探す手間、お釣りを受け取る手間が不要になります。具体的には、PayPayなどのおかげで個人間での建て替えや割り勘などがとっても便利になりましたね。 - ATM利用の削減
現金を引き出すためのATM手数料や、ATMに行く時間・手間を削減できます。
ATMを出先で探したり、ATMの手数料がかからない時間に頑張ってお金を下ろしにいくなどの手間が減りました。 - 支出管理の容易化
利用履歴がデータとして残るため、家計簿アプリなどと連携しやすく、支出の「見える化」が容易になります。 - ポイント還元などによる経済的利益
クレジットカードやQRコード決済の多くは、利用額に応じたポイント還元やキャッシュバックを提供しています。 - 衛生的
現金(紙幣や硬貨)に直接触れる必要がないため、衛生面でのメリットがあります。
事業者(店舗)のメリット
- 業務の効率化・生産性向上
レジ締め作業(売上と現金の照合)にかかる時間や、お釣りの計算・受け渡しの手間が大幅に削減されます。 - 現金管理コストとリスクの低減
売上金を銀行に入金する手間や手数料、釣銭の準備コストが削減されます。また、店舗に現金を置かないことで、盗難や紛失のリスクを低減できます。 - 販売機会の拡大
「現金を持ち合わせていない」という理由での購入機会の損失を防ぎます。また、高額商品が購入されやすくなる傾向(客単価の向上)も見られます。 - インバウンド(訪日外国人)需要の取り込み
海外ではキャッシュレスが主流の国も多く、決済手段に対応することで訪日外国人の利便性が高まり、売上増加が期待できます。 - データ利活用
購買データを分析し、顧客の属性や時間帯別の売れ筋商品を把握することで、マーケティングや在庫管理の最適化に活用できます。
社会全体のメリット
- 現金関連コストの削減
紙幣や硬貨の製造、発行、輸送、保管、廃棄にかかる社会的なコスト(ATMの維持管理費なども含む)を削減できます。 - 生産性の向上
社会全体で現金を取り扱う時間が削減され、その分の労働力を他の付加価値の高い業務に振り分けることができます。 - 取引の透明性向上
お金の流れがデータとして記録されるため、脱税やマネーロンダリング(資金洗浄)、偽札の流通といった不正行為の防止に繋がります。 - データ利活用によるイノベーション創出
決済データを活用した新たな金融サービス(FinTech)や、消費動向に基づいた新しいビジネスが生まれやすくなります。
出典:経済産業省「キャッシュレス・ビジョン」 (2018年4月)
一般社団法人キャッシュレス推進協議会「キャッシュレス・ロードマップ 2024」 (2024年12月)
経済産業省「キャッシュレス決済の動向整理」 (2023年7月)
キャッシュレス化のデメリット
キャッシュレス化には、消費者、事業者(店舗)、社会全体のにメリットの一方デメリットあります。
消費者・事業者、社会全体のメリットを確認していきましょう。
消費者のデメリットと課題
- セキュリティと不正利用のリスク
クレジットカード番号の盗用、フィッシング詐欺、アカウントの不正アクセスなどにより、意図しない決済が行われるリスクがあります。 - プライバシーへの懸念
決済データ(いつ、どこで、何を買ったか)が事業者に収集・分析されることに対し、プライバシー侵害ではないかという懸念があります。 - 通信障害・災害時の利用停止リスク
スマートフォン決済やカード決済は、電力供給や通信ネットワークに依存するため、停電時や通信障害時、大規模災害時には利用できなくなる恐れがあります。 - デジタルデバイド(利用格差)
スマートフォンやアプリの操作に不慣れな高齢者などにとって、キャッシュレス決済は利用のハードルが高く、情報格差がサービス利用の格差に繋がる可能性があります。
事業者(店舗)のデメリット
- 決済手数料の負担
売上金額に対して一定の割合(数%)の決済手数料が発生するため、利益率が低い事業者にとっては大きな負担となります。 - 導入コスト
決済端末(カードリーダーなど)の導入費用や、既存のレジシステム(POS)との連携・改修にコストがかかります。 - 入金サイクルの遅れ
現金商売とは異なり、決済(売上)から実際に入金されるまでに数日~数週間かかる場合があり、資金繰り(キャッシュフロー)に影響が出る可能性があります。
社会全体のデメリット
- 社会インフラとしての脆弱性
大規模な通信障害、電力の喪失(ブラックアウト)、システム障害が発生した場合、社会全体の決済機能が麻痺するリスクがあります。 - サイバーセキュリティの脅威
キャッシュレス決済システム全体が高度なサイバー攻撃の標的となる可能性があり、広範囲な情報漏洩やシステムダウンのリスクが常時存在します。
出典:経済産業省「キャッシュレス・ビジョン」 (2018年4月)
一般社団法人キャッシュレス推進協議会「キャッシュレス・ロードマップ 2024」 (2024年12月)
経済産業省「キャッシュレス決済の動向整理」 (2023年7月)
まとめ
キャッシュレス化は世界的な潮流となり、特にスウェーデンや中国、韓国といったキャッシュレス先進国ではすでに現金をほとんど使わない社会が実現しています。これらの国々では政府の政策やスマートフォン普及、国民の文化的背景がキャッシュレス化を後押しし、日常生活の隅々まで浸透しました。
一方、日本は2023年時点でキャッシュレス決済比率が39.3%にとどまりましたが、2024年には42.8%と政府目標の40%を前倒しで達成しました。クレジットカードやQRコード決済の普及が進んでいるものの、現金信仰や高齢者のデジタル利用の壁、中小店舗の導入コストなど課題も残っています。
キャッシュレス化には利便性や効率化、防犯効果といったメリットがある一方、個人情報やセキュリティリスクといった懸念も存在します。今後は現金とキャッシュレスの両立を前提としつつ、安全性と利便性を高めていくことが重要です。世界の動向を参考にしながら、日本独自のペースでキャッシュレス社会が発展していくと考えられます。